トランプ関税、トランプ相場で慌てている人も多いはず。
今回のファイナンシャル・ジャーニーではフィリップ証券永堀社長がトランプ関税と影響についてお話いただいています。
寝てました( ̄▽ ̄;) https://t.co/QvlbJBxrOF
— ヴェストラ (@vest_ride) April 9, 2025
 ヴェストラ
ヴェストラ必聴です
ファイナンシャル・ジャーニー概要


• 番組名:「ファイナンシャル・ジャーニー」
• 放送日時:毎週木曜日 8:30~8:49
• 放送局:ラジオNIKKEI第1
• 提供:フィリップ証券
• 出演者:
- 永堀 真氏(フィリップ証券 代表取締役社長)
- 門倉 貴史氏(エコノミスト/ブリックス経済研究所代表)
⸻



トランプ相場真っ只中のファイナンシャル・ジャーニー
📌 今回の放送テーマ:「関税がもたらす世界経済への衝撃と歴史の教訓」


「おはようございます。今日もよろしくお願いします!」
「はい、本日もスタジオからお届けしてまいります。さて永堀さん、今日はどんな話題でしょうか?」
そんな軽やかなやりとりから始まった今週の『ファイナンシャル・ジャーニー』。
テーマはずばり「関税」。最近のマーケットを大きく揺るがしている、トランプ氏の“関税政策”に焦点が当てられました。
⸻
✅ マーケットの最新動向:突然の関税発表、その影響は?
「いやー、今朝もびっくりしましたね。まさか“相互関税一部停止”の発表が出るとは」
と永堀社長。きっかけは、4月2日にトランプ前大統領が「世界共通課税10%、60カ国に対する上乗せ関税」を打ち出したこと。これにより株安・ドル安・債券市場の変動が一気に広がりました。
「ただ、アメリカ時間の午後に『90日間の猶予』という情報が出て、株価は急反発しましたね」
一見一安心のようですが、その裏にある緊張感は続いています。マーケットにとっては、一つの“揺さぶり”として受け止めるべき事態です。
⸻
✅ 歴史に学ぶ:関税の誤用が戦争を招いた過去
「実は、関税って歴史的にも非常に重要なテーマなんです」
と、永堀社長は話を1858年の日米修好通商条約にまでさかのぼります。当時の日本は「関税自主権」がなかったため、自国で関税率を決めることができず、それが独立国家としての資格を問われる要因となっていたとのこと。
さらに世界恐慌後、各国が高関税で経済を囲い込む「ブロック経済」に走った結果、日本・ドイツ・イタリアなどの“輸入依存国”が追い詰められ、第二次世界大戦へとつながったという流れを紹介。
「関税はただの経済政策じゃない。安全保障、ひいては戦争にもつながりかねないものなんです」
という永堀氏の言葉が響きます。
⸻
✅ 投資のヒント:「原料は海外製」が米国を苦しめる?


「今回のトランプ氏の狙いは、“アメリカ製品を売ること”だったようですが……」
実際には、現代の米国製品には多くの外国製の原材料や部品が含まれており、関税が上がれば最終価格も上昇。結果的に国内のインフレ圧力が高まると指摘されています。
「アナリストの予想では、インフレ率が2%以上上昇する可能性もあると言われているんですよね」
これでは、FRBが目指す「利下げ」にもブレーキがかかり、景気後退のリスクさえ出てくるとのこと。さらに他国が“報復関税”を行えば、輸出産業も打撃を受けるという、負のスパイラルに。
⸻
✅ 日本が見直すべきは「自給力」
「こうした国際秩序の変化を受けて、日本も考えるべきことがありますよね?」
という問いかけに、永堀社長が語ったのは「エネルギーと食料の自給率」。
• エネルギー:再生可能エネルギー、脱化石燃料のエコシステム構築
• 食料:カロリーベースでの自給率は現在38%、60年前の半分に
一方、アメリカは121%という驚異の数値。国の“生命力”として、自給力の強化が今後のキーポイントになるとのことでした。
⸻
🍜 東南アジアで即席麺がバブル状態!?――ASEANを動かす“ラーメン経済”とは
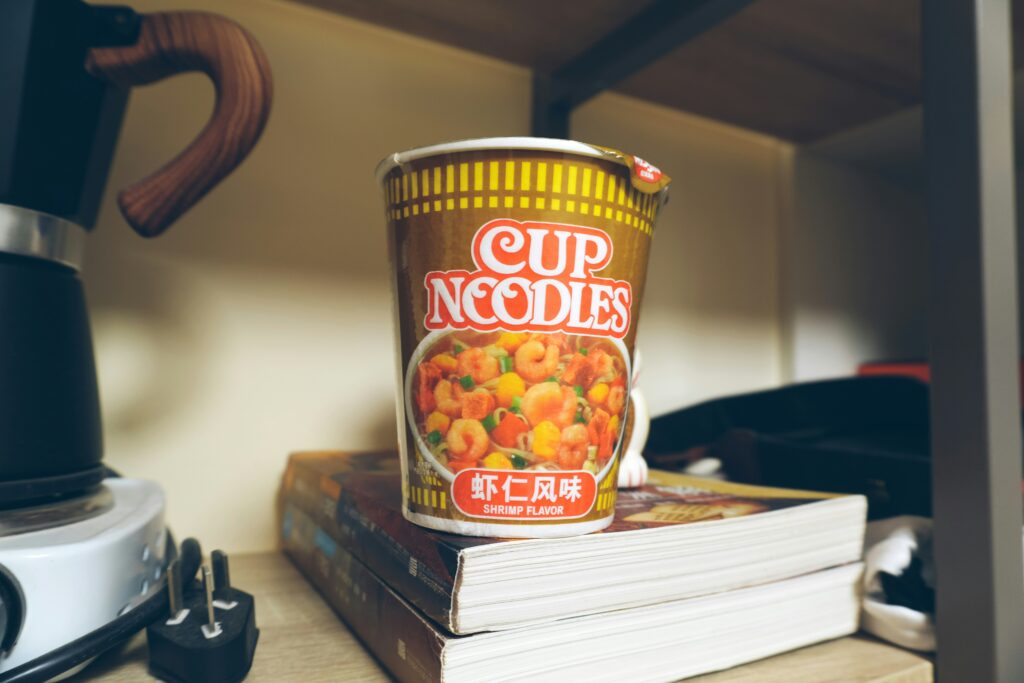
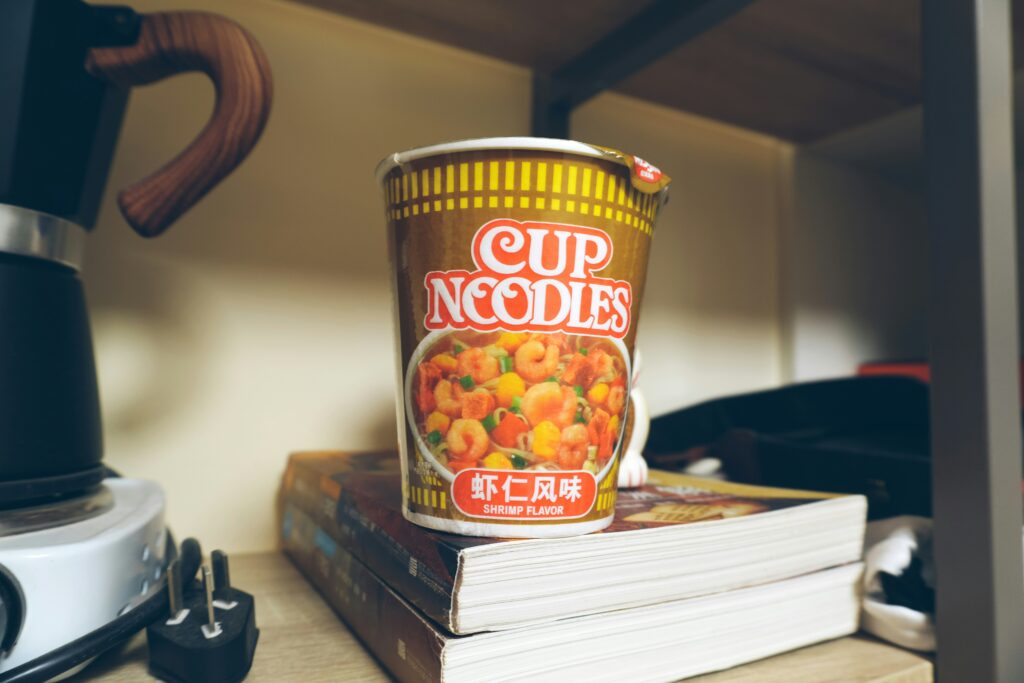
後半はエコノミスト・門倉貴史氏が登場。テーマは「東南アジアで即席麺が急成長中」。
「世界で年間1202億食も食べられているんですよ」と門倉さん。
「インスタントラーメンは日本が世界に誇る発明の一つ」――そう言われる時代が来るとは、1958年に日清食品の創業者・安藤百福氏がチキンラーメンを開発した当時、誰が想像したでしょうか。
しかし今、その即席麺が世界経済の中でもとりわけ熱を帯びている地域があります。
そう、東南アジア(ASEAN)です。
🍥 世界で1,202億食!即席麺の中心地は“東南アジア”へ
エコノミストの門倉氏によれば、2023年の世界即席麺消費量は年間1,202億食に達したとのこと。
そのうち約3割がASEAN地域で消費されています。
特に目を見張るのがベトナム。
ベトナム:消費量は2019年比で5割増!!


- 即席麺の歴史はベトナム戦争時代にさかのぼる
- 米軍の駐留によって持ち込まれ、戦後に国内へ浸透
- 近年は女性の社会進出と共働き世帯の増加で“時短食”として需要増
- 食品価格の上昇も、安価で手軽な即席麺を後押し
なかでも圧倒的な存在感を放つのが、日本の食品メーカーエースコックです。
「エースコックの市場シェアはなんと約4割。主力商品『ハオハオ』は、ベトナム国民にとって“国民食”のような存在になっています」
と門倉氏は紹介します。
ハオハオとは、エビ風味のスープに酸味と辛味を加えたユニークな味わいの麺。
2000年の発売から現在に至るまで大ヒットを記録し、同社の看板商品となっています。
さらに最近では、ノンフライタイプの健康志向商品も展開。
変化する生活様式と健康意識の高まりに対応しながら、エースコックは2024年には年間12億食の生産体制を視野に入れた新工場建設に着手するなど、供給拡大へも動いています。



まさに国民食ですね
🥢 フィリピン:7割のシェアを持つ“モンデ日清”


続いて注目すべきはフィリピン。
2023年の時点で、即席麺の年間消費量で世界7位を記録するなど、成長著しい市場です。
ここでトップシェアを握るのが「モンデ日清」という企業。
(※ただし、同名のフィリピン地場企業「モンデ」との合弁であり、日清食品との直接資本関係はないとのこと)。
人気商品は以下の通り:
- パンシット・カントン(焼きそばタイプ)
- 味はカラマンシー(すだちのような柑橘)やホットチリ味が人気
- 小腹用のミニサイズ「メリエンダ」向けカップ麺もヒット
フィリピンには**「メリエンダ」=軽食・おやつ**の文化があり、即席麺がこの時間帯の定番になっているというのも特徴です。



パンシット・カントンおいしそー
💡 即席麺は「生活インフラ」である
インスタントラーメンといえば“手軽な庶民食”の代表格ですが、東南アジアでは経済成長・都市化・インフレ対策・女性の社会進出といったマクロ要因すべてとリンクしています。
つまり、もはや単なる“食料”ではなく、生活インフラであり、社会構造の変化を映し出す鏡とも言えるのです。
そしてこの動きを捉え、品質で勝負する日本企業がしっかりと存在感を発揮している点も見逃せません。
✔ 放送内容の要点まとめ
- トランプ氏の「関税再発動」が世界経済に波紋を広げる
- 過去の教訓から見ても、関税政策には慎重な判断が必要
- 日本は「エネルギーと食料の自給力強化」が急務
- 東南アジアでは“即席麺ブーム”が継続、日本企業のチャンスも大
⸻
✔ 次回放送もお楽しみに!
次回の「ファイナンシャル・ジャーニー」は、また新たな視点で世界と経済を読み解きます。木曜日朝8:30、どうぞお聞き逃しなく!
⸻
✔ フィリップ証券で学ぶ、備える、投資する


今回の放送を聞いて、「もっと経済の背景を理解したい」「取引ルールを学びたい」と思った方は、フィリップ証券のセミナーをチェックしてみてください。
🎓【無料ウェブセミナー開催】
• タイトル:「プライスアクションで知る売買のチャンス」
• 日時:4月24日(木)20:00〜21:00
• 講師:陳正人 氏
• 👉 詳細・申込はこちら(フィリップ証券公式サイト)
フィリップMT5で、投資の旅をはじめましょう
\ 口座の申し込みは下記のボタンをクリック /
⸻
📝この記事は、ラジオNIKKEI「ファイナンシャル・ジャーニー」(2025年4月10日放送)の内容をもとに構成しています。









